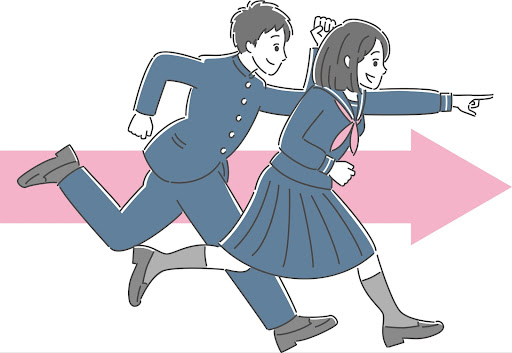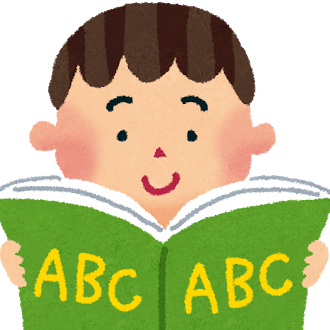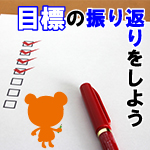メニュー
個別指導なら、ベスト個別。宮城県、山形県、福島県、栃木県、香川県の各教室で無料授業体験実施中!
勉強お役立ちコラム・セミナー
- 2025.07.16
- 全国の教育情報
中学校で最初につまずくのは英語?そのポイントとは
2020年の教科書改訂で小学校3年生から英語を学習するようになりました。
以前は中学校で初めて英語に触れる子と、英会話教室や学習塾で早くから英語を始めていた子とで大きな差がありましたから、その差が小さくなって英語が得意な子が増えそうですよね。
ところがフタを開けてみると、小学校の英語と中学校の英語のギャップに苦しみ、早い段階でつまずいてしまう子がとても多いのです。そのギャップとはいったい何でしょうか。
1つ前の記事を読まれていない方は先に読んでくださいね
習ったから知っているよね?いや、知らないけど…
ギャップの1つ目として、小学校での指導内容と中学校での指導内容がスムーズに接続されていないことがあげられます。
まず小学校では基本的に文法の説明はしません。YouのあとはareでSheのあとはisということはなんとなく知っていても、「be動詞」は?と聞かれるとわからない状態です。そのため中学校では文法を1から指導するように決められています。
ここまではよさそうですよね。
しかし小学校での学習が前提となっているため、以前の教科書と比べると覚える単語も文法も多く難しくなっています。内容が多くなれば、当然授業の進み方も速くなります。
「小学校で文法を教えてないから中学校で教えるけど、英語自体は4年もやってきたんだから速く進めてもいいよね」というわけです。中学校の先生にもよりますが、「習ったから知っているよね」という前提でどんどん進んでしまうケースもあるようです。
小学校では「成績が良い=英語が身についている」ではない
では中学校の速い授業についていける子とついていけない子の差はどこにあるのでしょうか?
実は、それが可視化されていないことも問題の1つです。小学校の英語の成績は授業態度が中心ですので、楽しく英語でお話しして授業に積極的に取り組んでいれば良い評価をもらいやすいです。
そのため同じA評価でも英語の基礎がどの程度身についているかに差があります。そしてその差に子どもも保護者も気づきにくいのです。
「楽しくて得意」から「点数がとれなくて苦手」に
評価方法の違いも大きな影響があります。
先述した通り小学校のときは積極的に授業に参加していれば良い評価がもらえました。「英語って楽しい、得意!」と思っている子も多いと思います。
ところが中学校の英語では「文法を理解する」「単語を覚える」「問題を解く」といったことが必要になります。「あれ、ちょっと難しいかも?」ととまどっているうちに定期テストになり、思ったより点数がとれずがっかり…。「点数がとれない=苦手」と感じてしまうのです。
小学校のテストで90点や100点をとることに慣れている子が、中学校の最初のテストで60点をとってしまえばとても落ち込むでしょう。
実際に中学1年生の英語の定期テストの平均点は以前にくらべかなり低くなっています。アルファベットと「私は〇〇です」を書くことができれば高得点がとれていた昔とは大違いです。
1度つまずくと追いつくのに時間がかかる
ご存じの通り、理科や社会は単元が独立していることが多く、途中でわからないところがあっても次の単元は理解することができます。例えば物理のテストでは点数がとれなかったけど生物は頑張ろう、と切り替えができます。
それに対して算数・英語は「積み重ねの教科」といわれ、1度つまずいてしまうとそれ以降の学習をスムーズに進めづらくなります。
英語であれば「be動詞と一般動詞」「三人称単数」といった基礎を理解していなければ、そのあとに学習する文法を理解することは難しくなるといったことです。
中学1年生の最初のつまずきでついた差は、3年間で雪だるま式に大きくなっていきます。
まとめ
ここまで小学校と中学校の英語のギャップについてお話してきました。
中学校の英語でつまずいてしまう子が多いのは事実ですが、お伝えしたいのは「中学校の英語ってこわい」ではなく、「早めに対策をたててつまずかないようにしましょう!」ということです。
こうしてお子様のために情報を集められている保護者様であれば大丈夫です。次のコラムでは小学生の間に始めたい、つまずきの予防についてまとめていきますね。
関連する記事
- ホーム
- 勉強お役立ちコラム・セミナー
- 中学校で最初につまずくのは英語?そのポイントとは